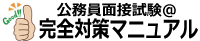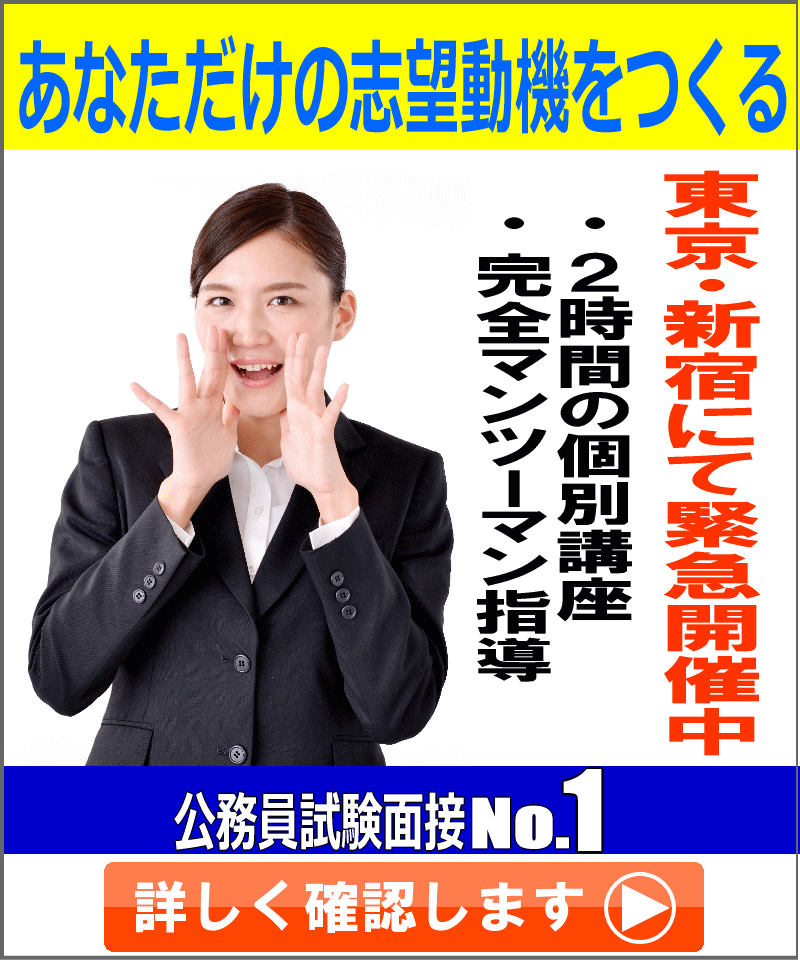集団面接は特に注意
公務員試験では、それほど集団面接は行なわれていません。特に、国家公務員試験ではごく一部だけに限定されています。
しかし、地方公務員の中では都道府県採用試験(いわゆる県庁採用試験)において広く行なわれています。集団面接では、周りの受験生と比較されますので、話し方ひとつで差が付くということもありますから注意が必要です。
話し方の基本
話し方の基本(1)からの続きとなります。
 3.長すぎず、短すぎず
3.長すぎず、短すぎず
面接試験は、面接官とのコミュニケーションです。例えるならば、面接官と受験生が「キャッチボール」をしていると考えてください。面接官の投げたボールをいつまでも抱えていると面接官はうんざりしてしまうでしょうし、あまりに早くボールを返してしまうと、今度は面接官は準備ができていないかも知れないのです。
長々と話すと、結局何が言いたいの?と結論や論点がブレてしまう可能性が高くなります。逆に、「はい」や「いいえ」だけで返してしまうと、面接官からすれば「それで?」となってしまいます。
どのくらいの長さが適切かというのは質問の内容にもよりますので一概に時間とかで決められるものではありませんが、回答の要旨を面接官に伝える程度に留めるのが無難です。それ以上に面接官が深く知りたい場合には、面接官の方から追加で質問されることになりますので、長いよりはやや短いくらい(あくまで伝えたいことの要旨が伝わるレベルで)がちょうど良いでしょう。
なお、自分の回答が終わったら「以上です」と一言添えると面接官に自分の回答が終わったことをアピールすることができます。
 4.面接官の目を見る
4.面接官の目を見る
面接中は、面接官の目を見て話すというのが基本です。これは面接に限ったことではなく、話をする時には話す相手を見るといのがマナーであり、ルールです。
しかし、これが苦手であるという受験生が多いのです。
目を見るのが苦手という受験生は、よく言われていますが、目ではなく、面接官の顔全体をボンヤリと見るようにすると良いでしょう。目を直視すると抵抗ある人でも、面接官の顔全体、あるいは鼻のあたりを見るようにすることで、面接官からすれば自分の目をしっかりと見ている印象を与えることができます。
話し方のポイント
基本を踏まえたうえで、今度は話し方のポイントをご紹介しておきます。
 結論先行で話す
結論先行で話す
端的にポイントを述べるためには、結論先行が好ましいと言えます。あらかじめ結論を述べた上で、それをより具体的に説明していく。
こうすることで、面接官は受験生が何をいいたいのかを事前に察知できるため、その後の具体的な話やエピソードなどについて安心・余裕を持って聞くことができるようになります。
結論を最初から述べずに、起承転結のように話をしながら最後に結論を述べるという方法もありますが、この方法は、
- 話が長くなる可能性が高い
- 短時間で行なう面接の回答方法としては不向き
- 結論に行き着くまでに矛盾を生じる可能性がある
- 結論が結論にならない可能性がある
といった弊害が考えられますのでオススメしません。どうしてもそういった話として組み立てたいという受験生は、上記の弊害を避けることができるように練習をしてから臨んだほうが無難です。