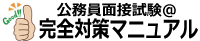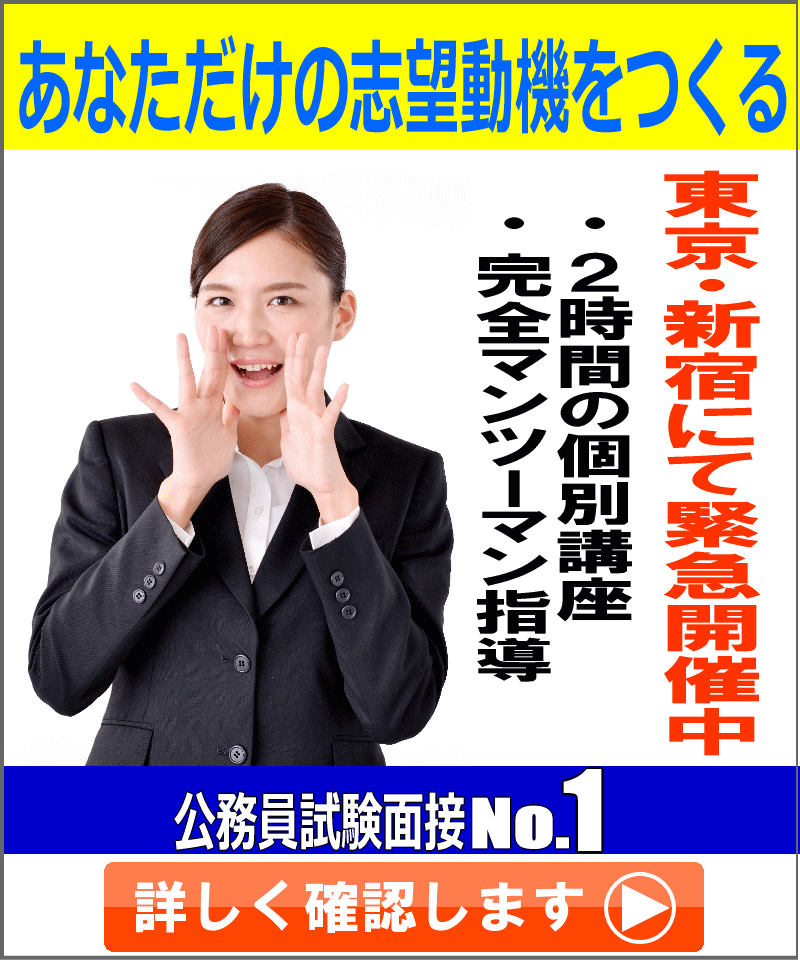そもそも面接試験の役割とは?
公務員試験には国家公務員・地方公務員という大きな区分けと、さまざまな職種に区分けされます。
しかし、全ての公務員試験に共通しているのが、「面接試験」です。なぜ、面接試験が公務員試験には存在しているのか?そんな当たり前だと思っているけれど、理由を問われるとなかなか答えることができない、その理由をまずは知っておきましょう。
人物重視へと移行する公務員試験
公務員試験は、まずは筆記試験を行うことで学力レベルによって選抜を行ないます。これは、ほぼ全ての公務員試験で共通しています。そして、筆記試験を通過した受験者に対して面接試験を行い、最終的な合格者を決定することになります。
この流れは、昔も現在も変わっていません。そして、昔までは「筆記試験に合格すれば面接試験で落ちることはない」と言われていました。
しかし、今は「面接試験で落ちる」受験生が増えています。つまり、面接試験は単なる顔合わせの場ではなく、より公務員としての適正を見るための「選抜試験」へと変貌したのです。
著しい環境の変化、時代の流れによって、公務員には今まで以上に多様でかつ優れた人材が求められています。民間企業では早くから、「学力ではその人材の全てを評価しえない」という事実のもと、面接試験にウエイトを置き始めていました。そして、公務員においてもその動きが加速化しています。
学力でははかることのできない、人物像にウエイトを置いて評価する。それが、面接試験の役割なのです。
公務員試験制度の改革によりより面接試験が重視されつつある
国家公務員の試験制度は、時代の流れによってより良いものへと改革がなされています。
平成5年度には、国家Ⅰ種試験(国家公務員1種試験)の一部において、面接で最上位の評価を受けた受験生には筆記試験の得点に一定の換算点を合算する判定方式が導入されました。
そして、平成9年度には、最上位に次ぐ段階の受験者にも同様の措置が取られるようになります。
さらに、平成10年度には、国家Ⅰ種の全部にこの措置が拡大され、国家Ⅱ種試験(国家公務員2種試験)にも導入されました。
その後、平成18年度には、まったく新たに面接評定の基準が導入されています。(平成17年8月「国家公務員採用Ⅰ種試験 6つの評定項目ごとに設定された着眼点別評定段階と行動の例」人事院)
このように、段階的に学力試験に加えて(あるいは学力試験以上に)公務員試験においては面接試験のウエイトが合否に与える影響として大きなものとなっているのです。
最近では、試験区分の名称変更や細分化が行なわれています。国家1種が総合職、国家2種が一般職へ、さらに試験形式なども多様化しつつあります。
この傾向は、国家公務員に限ったことではありません。地方公務員試験は国家公務員試験に準ずることが一般的で、例外なく地方公務員試験でも面接試験の重要性は高まっています。集団面接を行い、その後に個別面接を2回実施するなど、面接の回数を増やす自治体が増加傾向にあります。